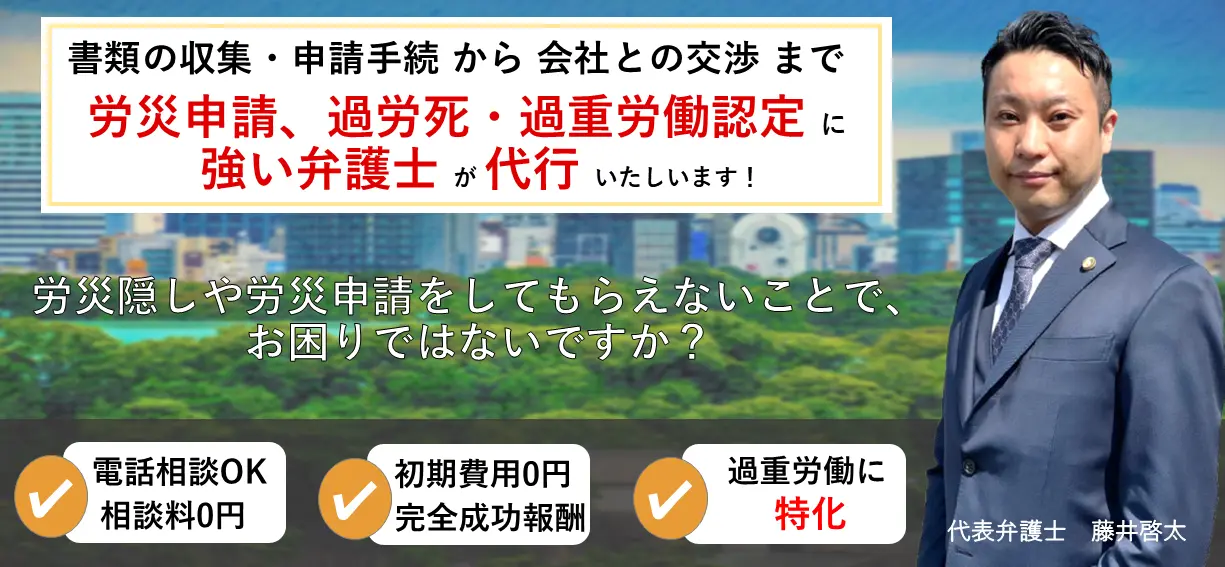労災手続に拒絶した会社に代わって、労災申請手続を行い、脳梗塞の原因が過重労働であると認定を受け、労災支給を獲得した事案
- 事案内容
- 依頼者(40代、男性)は、地場のトラック運転手として、連日に亘って長時間労働を行っていたところ、休日に脳梗塞を発症し、病院に緊急搬送され、入院となりました。
依頼者の妻は、夫が連日長時間労働を行っていることを気にかけていたことから、脳梗塞の原因は会社の業務にあると考え、会社に労災申請を要望しました。
しかし、会社は「脳梗塞は労災にならない」と述べて、一切取り合いませんでした。
困った依頼者の妻が当事務所に電話相談を行い、依頼者の妻から依頼を受けた当事務所の弁護士が入院中の依頼者の病室で出張法律相談を行いました。
その結果、労災認定を受ける可能性があると判断し、依頼者から労災申請全般及び会社への損害賠償請求のご依頼をいただきました。
詳しく見る
- 事案の経過
- 依頼を受けて、1か月以内に意見書を作成のうえで労災申請を行いました。
意見書作成にあたっては、手元に、依頼者の労働時間を証明する証拠はなかったので、依頼者から聴取した労働内容を詳細に記載し、その労働内容から合理的に推認可能な時間を計算し、過労死ラインを超過する労働であることを主張しました。
その後、追加の意見書として、依頼者は連続勤務が多く、拘束時間も非常に長いことなどを主張し、その裏付けとして同僚の陳述書を提出しました。
また、労働基準監督署の調査官による事情聴取の際には、脳梗塞の後遺症で発声が不自由になった依頼者の事情聴取を補助するために同席し、過重労働の事実を調査官に理解してもらえるように努めました。
その結果、労災申請から約10か月で脳梗塞の原因は会社の業務に起因するものであるとの労災認定を受け、休業補償給付の支給を受けることができました。
- 弁護士からのコメント
- 労災認定後、当事務所では、労災申請から損害賠償請求までワンストップで行いますので、損害賠償請求の資料のために、労災認定資料の開示を行いました。
そうすると、本件労災では、労働基準監督署が認定した労働時間は過労死基準の労働時間に僅かながら足りていなかったことが分かりました。
しかしながら、労働基準監督署は、長時間労働に加えて、連続勤務が多いことや拘束時間が長いことなどの理由を付加して、労働災害と認定していました。
全体的にこちら側に証拠が不足している事件ではありましたが、あきらめずに同僚の陳述書などを作成して証拠提出したことが功を奏したのだと思います。
なお、会社側も弁護士をつけて、会社に有利な主張を展開していたことが個人情報開示の結果分かりましたが、会社が労基署に提出した書類の内容までは確認することができないので、どのような主張となっているかはわかりませんでした。
脳梗塞など過重労働を原因とする労災は、会社側の協力は望めません。むしろ、本件のように会社は労災認定を妨害する目的で、会社に有利な書類を提出してきます。
そのため、過重労働を原因とする労災申請を行う場合には、自分で行おうとはせずに、労災手続に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
心停止(心臓死)の労災手続で、労災認定のために意見書の作成、会社への資料請求等を行い、心停止の原因が過重労働であると過労死認定を受け、労災支給を獲得した事案
- 事案内容
- 被災者(50代、男性)は警備員として、1勤務12時間の勤務シフトで連日に亘って長時間労働を行っていたところ、勤務時間中に心停止を発症し、死亡しました。
被災者の妻は、夫が連日長時間労働を行っていることを気にかけていたことから、心停止の原因は会社業務にあると考えていました。
しかし、会社は「被災者が自ら勤務シフトを組んでいたし、休憩時間もあったから長時間労働ではない」と述べて、過労死を否定しました。
困った被災者の妻が当事務所に相談を行い、当事務所で検討したところ、労災認定の可能性があると判断したので、遺族補償年金支給請求等の労災申請全般及び会社への損害賠償請求のご依頼をいただきました。
詳しく見る
- 事案の経過
- 依頼を受けて、1か月以内に意見書を作成のうえで労災申請を行いました。
また、労災申請と同時進行で会社に被災者の労働時間を証明する資料の開示を求め、過去3年分に亘る警備日報等の写しの開示を受けました。
開示を受けた警備日報を解析したところ、会社が休憩時間と主張している時間帯について、被災者は警備員の詰所で待機し、ワンオペ勤務を余儀なくされていたことが判明しました。
そこで、追加の意見書として、依頼者の勤務は全てワンオペ勤務であり、かつ、警備員という緊張を伴う職務であることからすれば、実際の「休憩時間」は一切存在しないことを主張しました。
また、会社に対しては、休憩時間と扱っていた部分についての未払賃金の請求も行いました。
以上で行った様々な手続の結果、最終的にこちら側の主張は概ね認められ、無事に被災者の労災認定は認められました。労災申請から労災認定まで約1年半を要しました。
- 弁護士からのコメント
- 本事件の労災認定にあたって、会社が主張する休憩時間の当否がもっとも重要な争点となりました。警備日報等の資料からワンオペ勤務であることが判明しなければ、会社主張の休憩時間がそのまま認定されていた可能性があります。
そうすると、被災者の労働時間が減るので、過労死認定も行われなかった可能性が高いです。
労災申請段階から弁護士に委任し、積極的に立証を行ったからこそ勝ち取ることが出来た労災認定であったと思います。
そのため、過重労働・過労死を原因とする労災申請を行う場合には、自分で行おうとはせずに、労災手続に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
なお、当事務所では、労災申請から損害賠償請求までワンストップで行いますので、本事件でも労災認定後は、会社に対して損害賠償請求を行っています。
会社が労災手続に無知で事故後1か月が経っても労災手続が進まず、困窮していたところ、会社に代わって、労災の各種手続の代理申請を行った事案
- 事案内容
- 依頼者(20代、男性)は、派遣労働者でしたが、派遣先の現場で荷崩れ事故に巻き込まれて、足に重傷を負う労災事故に被災しました。
労災事故であることは争いようがない状況でしたが、会社が労災申請に無知であったため労災手続に必要な書類が整わず、その結果、休業給付も受給できず、治療費も健康保険を使ってうえで、自己負担している状況でした。
今後の手続き等に強い不安を覚えた依頼者が当事務に相談し、未了となっている労災の各種手続の代理をご依頼いただきました。
詳しく見る
- 事案の経過
- まず、最初に会社代表者に連絡を取り、手元にある資料をこちらに全部送付させました。そのうえで、資料を整理し、不足分を整えるなどして、依頼を受けてから1週間程度で療養給付の書類を提出し、治療費を労災保険から支払われるように手続を行いました。
その後は、怪我で働けない分の労災補償である休業補償給付の手続き、健康保険を使用して既に支払ってしまった治療費の調整と清算の手続き、装具代の費用請求手続き、治療終了時に後遺症を申請する際に行う障害補償給付手続等、全ての手続を適時行っていきました。
また、障害補償給付手続を行う際には、診断書を取り寄せて、本人の怪我の状況を聞き、適切な後遺障害が認定されるようにアドバイス等も行いました。
その結果、後遺症の状態も適切に評価され、期待していたとおりの後遺障害の認定を受けることができました。
なお、当事務所では労災申請手続から損害賠償請求までをワンストップサービスで提供しているため、労災申請手続の完了後は、そのまま会社への損害賠償請求を行っております。
- 弁護士からのコメント
- 本来、労災申請は、わざわざ費用を掛けて弁護士に依頼しなくとも、当然に会社が手続を行います。
しかし、会社が労災手続について無知である場合や労災隠しなど手続を意図的に行ってくれない場合には、費用を掛けてでも労災手続の代理を依頼したほうが良いです。
本件でも、労災手続の依頼を受けることで、労働者にメリットのある労災手続を漏らすことなく、全て行うことができました。
特に、障害補償給付手続で後遺障害等級が決まりますので、後に損害賠償請求を行う場合には非常に重要な手続といえますので専門家にアドバイスを受けながら行うべき手続といえます。
本件でも、障害補償給付手続を行うにあたって、カルテ等を事前に検討してアドバイスを行い、その結果として、狙った通りの後遺障害等級を取得できましたので、依頼者様にも弁護士費用に見合ったサービスを提供することができ、ホッとしいたしました。
元請会社が労災手続を一切行わないため、病院代や休業金が労災保険から支給されず困窮していたところ、元受会社の労災隠しを労働基準監督署に申告し、元請会社の協力を得ないで、強制的に労災保険の各種手続の代理申請を行った事案
- 事案内容
- 依頼者(40代、男性)は、内装業に従事する労働者でした。
ある現場の内装作業に入った初日、開口部が空いているのに注意喚起が行われておらず、何も知らされていない依頼者は開口部から1階に墜落し、両脚を骨折する労災事故に被災しました。
本来であれば、建設工事なので元請会社が速やかに労災手続を行うべきでしたが、元請会社は何かと理由をつけて労災手続を行いませんでした。
そのため、依頼者は入院中の病院から労災の書類が提出できないなら治療費を自費で払ってほしいといわれるようになり、休業補償金を受給することができていなかったため、困窮しました。
元請会社の労災隠しに困った依頼者が当事務に相談し、労災隠しの対応、労災の各種手続の代理をご依頼いただきました。
詳しく見る
- 事案の経過
- 当事務所は、まず、最初に元請会社に連絡を取り、期限を設けて、期限内に労災手続に必要な書類をこちらに送付するように催促しました、
元請会社は対応するといいましたが、期限が過ぎても書類が届くことはありませんでした。また、こちらから督促の電話をしても応答してもらえませんでした。
そこで、今度は管轄の労働基準監督署に、元請会社が労災手続の書類を用意せず、事実上労災手続を拒否し、労災隠しを行っていることを書面にして、送付しました。
そのうえで元請会社が用意すべき労災書類が無い状態であっても、速やかに労災手続を進めるように主張しました。
その後、労働基準監督署の調査が行われ、こちら側の主張はすべて認められ、無事に労災保険の支給は開始されました。
また、労災保険支給開始後の休業補償請求や治療に用いる装具代の請求、治療終了後の後遺障害請求等の全ての手続もこちらで代理し、無事に後遺障害等級の取得もできました。
- 弁護士からのコメント
- 本件は、元請業者が労災手続を意図的に行わない労災隠しの事件です。
労災隠しは、元請や発注者への遠慮や労災保険への未加入など様々な理由で行われます。
労災隠しは、労災事故の証拠を揃えて、労働基準監督署に届出を行えば解決できることが多いです。
しかし、労災手続は、そもそも複雑ですし、事業者の協力が得られない場合にはもはや一般の人に解決することは困難といえます。
当事務所は、労災事故事件を数多く解決しており、労災隠し事件についても、多数の解決実績がありますので、お気軽にご相談ください。
労災事故に関する会社への損害賠償請求の依頼時に、別途、会社に対する未払賃金の存在が発覚したので、審査請求を行い、約150万円の労災給付の追加給付を受けた事案
- 事案内容
- 依頼者(40代、男性)は、建設工事の作業員として、様々な現場に派遣されていましたが、ある現場で現場監督の指示に従い、重機の傍で作業を行っていたところ、重機に接触して右手の指4本を失う重大事故に被災しました。
労災事故は現場監督の指示が原因で起こったものなので、依頼者は損害賠償請求を考え、当事務所に相談に訪れました。その際、依頼者から詳しい労働状況を確認したところ、労災事故の前から連続勤務が続いていたのにその分の割増賃金が未払であることが判明しました。
労災手続において、未払い割増賃金等が存在することが立証できれば、その未払い割増賃金の金額に応じて、支払われる労災保険給付額が高額になります。
そこで、当事務所は、事業者に対する損害賠償請求に加えて、労働基準監督署に対する審査請求も併せてご依頼いただきました。
詳しく見る
- 事案の経過
- まず、個人情報開示請求を行い、労災保険給付等で会社が労働基準監督署に提出している資料の開示を行いました。
そのうえで、労働局から開示された資料を精査し、残業代の未払を証明するうえで必要な資料を選別しました。
そして、審査請求手続において、こちらで計算した未払い残業代の計算書とその証拠を示し、給付基礎日額の計算のやり直しを求めました。
その結果、約半年後にこちらの主張は全面的に認められ、給付基礎日額が過去にさかのぼって修正され、不足していた給付分としてまとめて150万円程度が追加給付されました。
- 弁護士からのコメント
- 労災保険で支給される休業補償給付や障害補償給付の金額は、労災事故前3か月の間に支給された給与の平均日額を元に算出します。この元になる平均日額を「給付基礎日額」といい、労災手続においては極めて重要な要素となります。
しかし、労働基準監督署は、労災手続を受け付ける際に、労働者に未払残業代が存在するかどうかの調査までは行いません。そのため、本来、認められるべき給付基礎日額と労働基準監督署が認定する給付基礎日額との間で乖離が生じてしまいます。
当事務所は長年に亘って数多くの未払残業代請求を行ってきました。そのため、労働者の働き方や契約内容、労働時間の管理態様を聞くだけで、証拠上、未払残業代の請求が可能かどうかの判断ができます。
そして、労災事故の相談を受けるにあたって、未払残業代の有無も併せて聴取し、請求が可能であれば積極的に審査請求を行い、給付基礎日額の上方修正を行っています。
これらの請求は着手金無料・完全成功報酬制で行っており、依頼者様にとってもリスクのない契約となっています。
労災事故に遭われて、「労災保険で支給される金額が少ない」と感じている場合には、追加で支給を受けられる可能性もありますので、お気軽に当事務所までご相談ください。